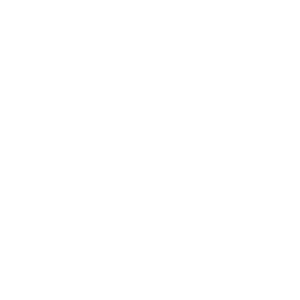アメリカを拠点に活動する若手新人監督との出会い
――映画『僕の中に咲く花火』には、どういう経緯で出演することになったのでしょうか。
加藤雅也(以下、加藤) 清水友翔監督とは、とあるパーティーで出会ったんです。集まっていたのは40代ぐらいから僕ぐらいの年齢の人たち。そんな中に二十歳そこそこの彼が混じっていて、たまたま横に座ったので、「何してるの?」と聞いたら、「映画を勉強してます」と。今度、日本で映画を撮ることを考えているというので、「じゃあ一回撮ったものを見せて欲しい」みたいな話をしていたら、彼が「映画を撮るにあたって、アメリカと日本の違いは何ですか?」と聞いてくるんです。

――清水監督はアメリカを拠点に活動しているんですよね。
加藤 そうです。彼から「アメリカに帰る前に、いろいろ聞いておきたいことがあります」ということで、何度か会って、アメリカと日本のシステムの違いについて詳しく説明しました。その後、彼はアメリカに帰って、また日本にロケハンに来るというのでそのときにまた会って「こういう作品に出ていただけませんか?」というオファーがあったんです。頑張っている彼を応援したい気持ちもあったので出演を決めました。
――脚本を読んだときは、どんな印象を持ちましたか。
加藤 すごくいい話ではあるけど、エンターテイメントじゃないから、当たるか当たらないかで言えば、今の日本において難しいところのある作品だよね、ということは正直に言いました。「これは自伝なの?」と聞いたら、「そういう部分もあります」という答えだったので、だったら面白いだろうなと。自分のことがある程度ダブっているのであれば、いいものになる可能性も高いですからね。
――そこまで若い監督と、加藤さんのようにキャリアのある俳優さんが密にコミュニケーションを取るのは珍しいことですよね。
加藤 30歳以上も年が離れていると、積極的に「どうですか?」って聞きづらい部分があると思うんです。でも遠慮せずに聞いてくる姿勢は大事なことだと思います。僕もアメリカに行った時期があるので、彼の苦労も分かります。日本に戻って映画を撮るには、アメリカとシステムが全然違うから、大変なんですよね。頭の中がガチガチのままアメリカのシステムでやろうとすると日本はそうじゃないところもあります。特にバジェットに関しては、映画監督としてヒットさせたら次が撮れるというのがある。たとえヒットしなくても、作れるなら作っていいというものでもない。やっぱり投資してくださる方に対して、損はさせないようにするのが基本。それでも応援するよという出資者がいたとしたら、自ずと大作にはならないのではないかと思います。あくまで持論ですが。
――当初、清水監督はどれぐらいの規模感を想定していたのでしょう。
加藤 「何人ぐらい想定してるの?」ってスタッフの数を聞いたら、明らかに多すぎるので、「そんなに大人数だと予算的に難しいと思うよ」という話をしました。DOP(撮影監督)がいて、オペレーターがいて、ピントマンがいて、ということではなくて、できるだけ最小限に絞る。映像に関してもそうだけど、音に関しても、ライティングに関しても、いろんなことを絞らないといけない。理想通りにやっていたのでは、すごくお金がかかるし、バジェットのことも考えてやらなきゃダメだよという話をしました。

――キャスティングについての相談もあったのですか。
加藤 そこまでは関与していないですが、脚本を読んだときに、この役のイメージは渡辺哲さんだなと思って、それを清水監督に伝えたら、「僕も同じ意見なんです」という話になって。それで僕が哲さんのところに行って、「こういう脚本があるので一度読んでもらえませんか?」とお願いしたら、哲さんも「やるやる」って快諾してくれたんです。そのほかのキャスティングも監督自身が決めていました。中でも主人公とヒロインの二人はこわだっていて、主人公の大倉稔を演じた安部伊織さんは、どこか監督と似ているんです。
——長編映画デビュー作で、キャスティングの希望が通るのもすごいことですね。
加藤 その辺はプロデューサーの落合賢さんが、清水監督の意図を汲んでキャスティングをされたんだろうなぁと思います。プロデューサー目線で言うと、潤沢な予算がある訳でもないから、初主演の子よりもキャリアのある俳優のほうが宣伝になると考えるはずです。でも落合さんが監督の意思を尊重して実現したキャスティングだと思います。
――『僕の中に咲く花火』はセリフに頼らない演出が印象的でした。
加藤 彼の短編映画を見たときにも感じたのですが、やたらと喋らない。セリフに頼らず、カットで見せていく、状況で見せていくというのが彼の作風であり、映画はそうであるべきと思いました。完成した『僕の中に咲く花火』を見ても、この年齢で、このキャリアで、ここまでしっかりと撮れているから、その才能には驚きます。
――画面の質感も素晴らしかったです。
加藤 DOPが清水監督とアメリカでも組んでいる有近るいさんで、彼女が映像を作って、日本側のオペレーターが回していくという形でした。長編デビュー作で、ゴダールのように映像のクオリティを無視して低予算で作っていくのも手ですが、この映画のように商業的にちゃんと撮るのが素晴らしい。インディーズとは思えないほど、よくやってますよね。それなりのキャリアで独立してやってる人でも、なかなか撮れない映像になっていますよ。初めて試写で見たとき、岐阜の湿度の高い夏の暑さがよく出ていて、「これどうやって撮ったの?」って有近さんに聞いたんです。そしたらアメリカで開発された特殊なレンズで、最近流行っているんですよと。フィルターが違うらしいんですが、ぬめっとした質感が出て、そういうところにもこだわっているんです。
――日本の土着感が上手く出ていますよね。
加藤 カメラは映像を撮るんじゃなくて、空気感を撮らなきゃいけないんです。湿度や暑さって直接は映らないじゃないですか。雨や風を映すのは比較的に簡単だと言われるけど、太陽にカメラを向けることは、すごいチャレンジなんです。その湿度感が出ていたのは、この映画の中でもすごく頑張っている一つですね。そのフィルターは高価らしいんですが、彼らが通っていたアメリカの映画学校は、卒業した生徒にも「何年間は援助しますよ」と安く貸してくれる制度があるらしいです。