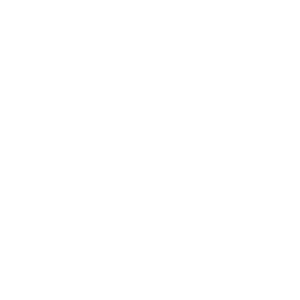十代の頃は優等生であることが苦痛だった
――新曲について1曲ずつお聞きします。冒頭を飾る「twelve」は、アコースティックを基調にした温かみのある楽曲です。
楠木 実は最後にできた曲なんですよね。アルバムのコンセプトがはっきりしていたので、皆さんに一つの作品として没入していただきたいなと考えた時に、オープニング的な、アルバムの世界にしっかり入り込んでもらえるような楽曲を1曲目に配置したいなと思ったんです。そこでアルバムの世界観をおとぎ話に例えて、絵本の冒頭を読んでいるような、まだ全貌は分からないけど、何かがこの後にあるんだろうなという、引っかかりのある曲にしたかったんです。だからポップスの王道である「平歌」「サビ」みたいな構成に捉われずに作りました。

――編曲はarabesque Choche(Chouchou)さんです。
楠木 ゲーム音楽のように、ずっと聴いていてもストレスがないような、なおかつ世界観がしっかりあるという楽曲にしたいなと考えた時に、arabesqueさんが作られる寓話っぽい、非現実的な世界観がいいなと思ったんです。以前ご一緒した時も、私のイメージを音にするという部分で相性が良くて、やりやすさを感じていました。「こういう雰囲気がいい」「こういう楽器を使いたい。でも、この楽器は使いたくない」「こういう情景が浮かぶものにしたい」など、私は音楽用語で話すわけではなく、イメージをお伝えする形になるんですけど、私のイメージ通り、またはそれ以上に形にしてくださる方なので、信頼を持ってお願いさせていただきました。
――サブスクの普及もあって、曲単位で聴く若い世代が多い中、アルバムをコンセプチュアルに作るのは難しい時代です。楠木さん自身、アルバム単位で聴くことが多いんですか。
楠木 多いですね。もちろんシャッフルで聴くこともあるんですけど、どうしてこういう曲順にしたんだろうとか、アルバムに込めた思い、全体的な雰囲気を感じられる瞬間が好きなんです。声優としてアニメに携わっている身としては、アニメファンの方々は音楽を聴く時もストーリーやコンセプトなど、作品として捉えることができる人が多いなと感じています。特に私の曲を聴いてくださる人たちは、その親和性があると思うので、こういう聴き方もあるんだよというのをご提案したい気持ちもあって、アルバムの構成にこだわっている部分があります。
――すぐに歌が始まる曲が多い中、イントロが長い曲も多いですよね。
楠木 自分の聴いてきた音楽が、イントロが魅力的な曲が多いので、自然とイントロもそういう形になっています。
――5曲目の「優等生」は、どのように生まれたのでしょうか。
楠木 今回のアルバムはターゲットを絞ったとお話しましたが、ではどういう人に聴いてほしいかを具体的に考えた時に、今まで自分が共感してもらえなかったことを思い返して生まれた曲です。
――楠木さんの経験を書いたということでしょうか。
楠木 そうです。私は中学生くらいまで、自分で言うのもなんですが優等生をしていまして、それが苦痛だったんです。尊敬する人、大事にしたい人などから、「優等生であってほしい」という願望を感じるのでそうしているけど、無理をしている自分がいて。よくある話ですけど、不良が更生すると褒められるのに、元から優等生は褒められないことに、すごくモヤモヤする学生時代を送っていて。その上、優れた者の悩みは深刻な悩みとして受け取ってもらいにくくて、「そんなの自慢じゃないか」「自分のことを優れていると思っているんだ」と切り捨てられて、なかなか共感されなかったんです。ただ、この年齢になって、いろんな人たちの話を聞いていると、そういう人は意外と多いんですよね。なのに、優等生としての悩みや、そう見られたくなかったけど頑張っていた人たちの悩みに寄り添う曲は今まであまり出会ったことがなくて。だから、「優れた」という部分にフォーカスした楽曲を作ってみたいと思ったのがきっかけでした。

――歌詞がストレートですよね。
楠木 この曲に関しては、回りくどくしたら、伝わり方が変わりそうだなと思ったので、とにかく真っすぐ書くというのを意識しました。
――不穏さを感じさせるスリリングなサウンドも歌詞の世界観にマッチしています。
楠木 私はバンドサウンドの楽曲が多いんですけど、この曲は打ち込みでお願いしていて。打ち込みは揺らぎがなくて、カッチリしているのが優等生っぽいなと思ったんです。もともと重永亮介さんから送られてきた第一稿は、ラスボスみたいな余裕を感じる、ずっと勝ち続けてきましたという強さを感じました。でも私が届けたい人はそうじゃなくて、ギリギリで戦っている人や今にも壊れてしまいそうな人、脆さがある人だったので、もっとヒリヒリしたアレンジにしてくださいとお願いして、今の形に落ち着きました。歌詞の強さと、アレンジの脆さのアンバランスが揃って、やっと私の描きたいものになると思ったので、何度かやり取りをさせていただきました。
――アレンジャーの方と何度もやり取りすることは多いんですか。
楠木 第一稿で完璧な場合もあれば、「優等生」みたいに何度もやり取りする場合もあります。私から「もっとこうしてみたい」と具体的に提案するというよりは、自分の中にあるイメージにどれだけ近づけられるか、もしくはそれを超えたものを得られるかみたいなところなので、すり合わせるという感覚が近いかもしれないです。
――重永さんの編曲が多いのは、どういう理由があるのでしょうか。
楠木 とにかく引き出しが多いんですよね。明るい曲も、暗い曲も、どんな曲でも対応していただける。あと重永さんは仕上げてくださるのが早いので、それだけ自分がこだわりたい部分を突き詰める時間ができるんです。また音数が多くても散らからないし、ポップスとして華があります。耳に残るアレンジや仕掛けを入れてくださることが多いので、楽曲に華やかさを持たせたい時や、ポップスに意識が向いている時はお願いすることが多いですね。