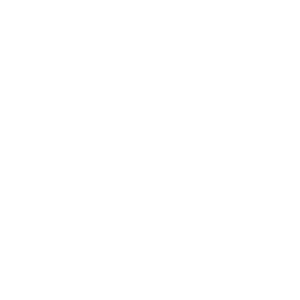夫婦の関係性の中で二人のすれ違いを描きたかった
――映画『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』は日本×台湾×アメリカの合作で、真利⼦監督のオリジナル企画・脚本ですが、どのように制作がスタートしたのでしょうか。
真利⼦哲也(以下、真利子) 2019年からハーバード大学の客員研究員として1年間、ボストンに滞在した後、コロナによる国家非常事態宣言が発令されて、日常が止まってしまいました。その間、アメリカの友人たちと一緒に『MAYDAY』(20)という作品を撮ったりしていたのですが、そういう生活の中で脚本を作っていきました。

――アメリカでの経験が作品に影響を与えた面はありますか。
真利子 日本だけでやっていたときよりも、視野が広がったというか。僕が住んでいた場所が学生街だったので、いろんな国の人たちがいる環境でした。アカデミックな環境で、様々な影響を受けながら生活していたことは少なからず脚本に影響しています。
――言語の壁で苦労したことはありましたか。
真利子 多言語の現場でしたが集まった人たちのおかげで、言語の壁みたいなものはあまり感じなくて、大きな障害にならなかったというのが実感でした。映画制作は十分なコミュニケーションを取る必要はありますが、文化の違いはあったものの、試行錯誤をしながら、抵抗なくやっていくことができました。
――夫婦を物語の中心に据えた理由は?
真利子 主人公の賢治(西島秀俊)と妻のジェーン(グイ・ルンメイ)との関係性の中で二人のすれ違いを描きたかったんですよね。その上で二人の間に子どもがいるのも、重要でした。ニューヨークのブルックリンに住むアジア系の家族の悲劇を描くにあたって、その大枠となるアメリカの社会を取材しながら、誘拐事件に関わる若い男女や熟練の刑事も描いて、少しずつ世界を広げていきました。
――ジェーンは人形劇に携わっており、人形劇の練習と公演が映画でも需要な役割を果たします。どういう意図があったのでしょうか。
真利子 賢治は過去の記憶を動機として大学で廃墟を研究しています。劇中でルナティックシアターという廃墟の劇場が出てきますが、そこで二人は出会った。そうなるとジェーンはあの場でパフォーマンスできるアーティストにぴったりでした。人形劇についてはアメリカ滞在中、たまたま日本から来た友人が人形劇を志していて、そのときに初めて存在を知ったんです。自分の思い描いていた人形劇は「ひょっこりひょうたん島」のような子供向けのものだったのですが、そこで知った人形劇は政治的なメッセージがあって台本が手書きで書いてあったり、人形が大きかったりとカルチャーショックでした。そういうアバンギャルドでアンダーグラウンドな人形劇をジェーンがやっていて、それが廃墟という場所と、かつて彼らが出会った場所、そして職業とが一致したんです。
――スタッフも日本人と海外の方がミックスされています。
真利子 日本から連れて行ったスタッフはカメラマンの佐々木(靖之)さんと録音の金地(宏晃)くんの二人で、あとは現地で採用したスタッフでした。
――この映画を構想するにあたって、最初から海外の方を中心にスタッフを組むことは決めていたのでしょうか?
真利子 アメリカの撮影システムは日本と全然違うので、トライアンドエラーしながら、佐々木さんと金地くんと一緒に長編をやるというのは最初から考えていました。その前に二人と一緒にシカゴで『Before Anyone Else』(23)という、『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』につながる短編を撮ったのですが、現地のスタッフたちが集まって、仕組みの違いや、何が足りないか、何が必要かも分かってきました。日本と大きくルールは違うけど、やっていること自体は変わらなかったので、現場となるニューヨークのスタッフを集めて撮影しました。
――労働条件なども全く違うと思うのですが、そのあたりはいかがでしたか?
真利子 完全にアメリカのルールで撮影して、大変でしたが見習うべきところがたくさんありました。彼らは当然ながら、生活の中で映画を撮影しています。子役の労働時間は厳格に定められていたり、男女問わず俳優に年齢を聞いてはいけないとか、いろいろな常識を理解した上で、どこまで自分たちのやりたいことができるかが課題でした。まずは余計な時間の浪費を減らすため、早めに全シーンのショットリストを作ってスタッフに共有する必要がありました。オーバータイムしてしまうと、現場の士気も下がるし、お金もかかって映画が崩壊してしまう。そうならないように、その日に何カット撮影するかを決めて、撮りきれないと思ったら、その場で「ここは減らそう」と判断して、なんとか時間内に終わるようにしていました。
――事前にショットリストを共有して、スムーズに進行するものですか。
真利子 必ずしもその通りになる訳でもなく、いくら準備しても完全にシステマティックに人が動くかというと、そうはいかなくて。日々、誰かが忘れ物をするみたいなことが起こるんです。でも、その誤差が映画の良さでもあり、その度にストレスを溜めてもしょうがないので、ゲームのように楽しんで取り組みました。撮影スタートが遅れることもありましたが、それを踏まえて臨機応変にやっていきました。