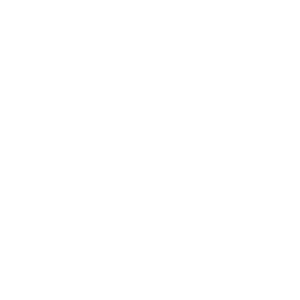ルールから逸脱しなければ何をやったっていいのが演劇のルール
――熱量がすごいというお話がありましたが、つか作品は、どれも役者同士がエネルギーをぶつけ合うような舞台で、演じる側として大変かと思います。
小澤 大変ですよ。稽古から手を抜けないですからね。でも手を抜いたら、つか作品をやる意味がなくなってしまう。たとえ稽古といえども、それをやらないで流すのは本末転倒です。どこまで自分が持っているエネルギーを2時間出せるかが重要で、劇中にたまたまセリフがあって、たまたま動きがあって、たまたま演出があるだけで、最初から役者は丸裸になるつもりで、どういう風にエネルギーを出していくかを考えるしかない。とりあえず百本ノックしようみたいな、ある種、部活なんですよね。これ意味あるの?って思うこともあるけど、それが5年後、10年後に活きてくるんです。

――演出家が変わっても、つか作品へのアプローチは変わらないんですか?
小澤 見せ方やテクニックの部分は変わりますけど、根底にあるものは変わりません。結局、エネルギーを出さないと伝わらないんです。お金を払って観に来てくれる人たちに対して、演劇の持つエネルギーや引き付ける力を出し続けていかないと伝わるものも伝わりません。
日比 どれぐらい熱量を持ってやれるかということですよね。あとは共演者の方々との相性もあると思うので、お稽古で積み重ねながらできたものを精一杯お届けするだけかなと思っています。
小澤 作品には必ずルールがあるじゃないですか。たとえば決まった時間があって、その中に何人の役者が出ていて、これぐらいのセリフの量があって、椅子取りゲームのように役者が席を取って、役割分担して一つの作品ができあがる。その中で伝えたいものは何なのかというお題を理解して、そこのルールから逸脱しなければ何をやったっていい。それが演劇のルールだと思います。それが発揮できるかどうかは役者次第。でも不正解はないんですよ。演出家が気に入るかどうかはあっても、できあがったものをお客さんが観て、それが正解になるんです。

――こぐれ修さんの演出については、どんな印象をお持ちですか。
小澤 もともと、つかさんと一緒にお仕事されていた方ですし、つか作品についても一番詳しいんじゃないかというぐらい理解しているんです。音で覚えている人なので、セリフの話し方にしても、つかさんならこうするだろうなというのが分かっている。つかさんが培ってきたそのままのセリフを、そのままやろうというスタンスなんですよね。オリジナルの戯曲のままで、どれだけ役者が演じられるかが今回の課題ですし、その点では信頼のおける演出家です。
日比 小澤さんの言う通り、音で覚えていらっしゃる方で、いろんな提案をしてくださるんです。「こう言ってみて」と一つじゃなくいろんなパターンを試して、「これだ!」というのを見つけるまで一緒に模索してくださるんですよね。