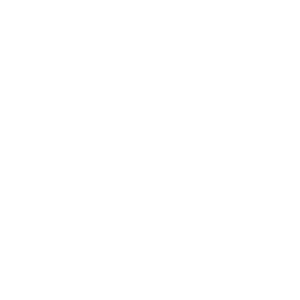大きい会場でのテンションコントロールは課題の一つ
――前回に引き続きアリーナ単独公演「“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama」の振り返りをお願いしたいのですが、後半はテクニカル面をお伺いします。まずは映像について。
Novel Core サービスLEDをそのまま生かすのか、生カメの上にエフェクトをかぶせるのか、かぶせるとしたら歌詞を出すのか、何かマスクをかけるのか、エフェクトをかけるのかといったことを、映像チームが演出ミーティングを組んで、1曲ずつ全員で指差し確認をしているタイミングで、僕からの指示を出させてもらいました。リハーサルを進めていく中でも、ここはトゥーマッチな気がする、ここは歌詞が出たほうがいい気がするなどが出てきたので、演出のKOSUKEくんから意見をもらいながら、みんなでブラッシュアップしていきました。

――ステージセットはどのように決まっていったんですか。
Novel Core もともと4パターンのステージプランがあって、大まかに言うと一番足し算をしたパターンと、一番引き算をしたパターンという2パターン。足し算したパターンは、バルーンを中心にローラーコースターのレールを模したトラスが走ったり、カフェテラスみたいなセットを組んだり、センターステージに向かうキャットウォークとCステ自体も全部床面がLEDだったり、左右のサービスモニターを円形にしたり、やれることは全部やります、みたいな。当初はそれで進行していたんですが、僕がいろんなアリーナ規模のサイズのライブを去年いろいろ観させてもらって。演出過多になるとライブ感が薄れるのと、コンセプトが強くなり過ぎて僕っぽくないのかもなという懸念が出てきて。今の僕らがやるべきことはそれじゃないなということで、演出を大幅に削らせてもらって、バルーンだけは残した上で一番ストイックだった今回のステージプランに落ち着きました。
――照明も今までにない試みが多かったかと思います。
Novel Core 今回は特殊で、今までなかったことで言うと照明が3層になっていて。いつも通り龍﨑くんの照明が軸にあって、今回はレーザーを初めてライブに入れるというところでアカリセンターのチームに入ってもらいました。もう一つ、ステージ上に電飾が這わせてあって、それを担当する照明オペレーションの方にも入ってもらって。だから普段よりも連携は大変だったと思います。純粋に3オペレーションになるだけだったらいいんですけど、あの規模の会場だと引き算のほうが生きることも多いので、全部が全部一気に出る瞬間をいっぱい作るというよりは、レーザーだけにする瞬間、普通の生のサス(サスペンションライト)とか龍﨑くんの生っぽい照明だけを生かす瞬間、逆に全ての照明を消してお客さんのフラッシュライトに委ねる瞬間、電飾だけを一瞬だけ点灯させて消す瞬間などなど。各セクション、3名のオペレーターがちゃんと息を合わせて、足し算引き算をしないと絶対にいい画にならないというのがあったので、しっかりとミーティングでやり取りさせてもらって。ただ武道館公演あたりから、龍﨑くんの照明に関しては、僕からのオーダーシートは一つも作ってなくて。基本的に全部任せても心配がないというか、僕の好みも理解してくれているんです。龍﨑くんのほうで気になったところがあったら、「どっちのほうがいいと思う?」と聞いてくれるし、コミュニケーションはスムーズでした。
――映像と照明の連携も重要ですよね。
Novel Core 仰る通りで、特に生カメにリアルタイムでエフェクトをかける演出、たとえば「DOG」でやったような演出のときはステージの明るさ、僕自身に当たっている光の色、ストロボのスピードなどによってエフェクトのかかり方が変わっちゃうんですよね。僕の顔が潰れちゃったり、逆にエフェクトがかかりづらかったりしちゃう。でも、そこは現地でしかシミュレーションできないから、事前に照明チームのオペレーションと映像送出チームのオペレーションがちゃんと噛み合わなきゃいけない。そこはKOSUKEくんが間に入って丁寧にやってくれました。
――衣装についてもお聞きします。事前にそこまで統一しないと仰っていましたが、22名のダンサーズは統一感があったように思います。
Novel Core 僕からリクエストしたのはカラーぐらいですかね。さすがに人数が多いのでモノトーンで統一して欲しいと伝えて、事前にみんなからLINEのアルバムで写真をもらって、全体のバランスを見た上で僕から指示させてもらってというのはあったんですが、みんなおしゃれなので何の問題もなく、特にフィードバックするとかもなく、あの感じになりました。THE WILL RABBITSもそうですね。各メンバーから写真をもらって、クマさん(クマガイユウヤ)がこういうアイテムを使うんだったら、ドラムの(佐藤)響さんはこっちのトップスのほうがいいかもねというやり取りをしましたが、基本はお任せでした。

――公演を終えて、新たに見つかったバンドの課題はありましたか。
Novel Core 公演の最後のほうで、ようやく「このぐらい力が抜けていていいんだ」と気付いたところがあって。全体を通して、ちゃんと僕もバンドメンバーも力んでいたんですよね。終わった後に響さんも、「思ったよりも体力を使って、後半はバテちゃった」みたいなことを言ってて。僕もパフォーマンスをしながら、少しドラムがよれているなと気付いたんですが、それは僕も含めて全員にあったことで。それって体力配分というよりは、もう少し力を抜く必要があるんだと感じたんです。それが上手くいったのが後半の「WAGAMAMA MONDAIJI」で、やっている最中に「これだ」としっくりくる感覚がありました。
――必要以上に力が入った原因は何だったんですか。
Novel Core やっぱり大きい会場だと客席との距離があるんで、届けなきゃという気持ちが先行すると、どうしても声は大きくなるし、普段しない発声が出ちゃったりもします。体の動きも普段より力が入っているから、より疲れるんですよね。ただ今回の経験があるので、また同じ規模の会場で単独をやるってなったときは慣れもあるし、ちゃんと力を抜けると思うんですが、テンションコントロールは課題の一つですね。あと永遠に尽きない課題なんですが、曲と曲の繋ぎをもっと面白くできる余白はいっぱいあるなと。そのためにはシームレスクロスをもう少し工夫する。特にそこは今回の公演でKOTAくんに意識してもらいたくて、あえてDJセクションを組んで試したところもあります。KOTAくん自身も、ライブが終わった後に「やりたいこといっぱい出てきた」と言ってました。ヒップホップの基本中の基本というか、曲と曲の繋ぎを卓で回す人が工夫して、いかにストレスなく次の曲に行けるかが課題だと思います。DJの曲の繋ぎ方は絶対にもっと良くなるし、僕もMCだったり、曲と曲の間に入る一言だったりで、もっと気の利いたことが言えるようになるなって公演中に感じました。
――まさに5月2日から始まる「“BACK TO AGF” TOUR 2025」はDJの繋ぎが重要になってきます。
Novel Core 全国16ヶ所、全17公演中、DJセットが14公演あるので、KOTAくんと僕でちゃんと話し合って、面白い繋ぎを試していきます。