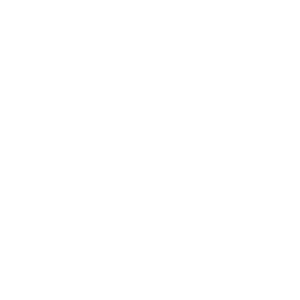極力、顔の可動域を使わないように意識した
――6人の別人でありながら、同じ“ある男”ということで、工夫したことはありますか。
香川 橋渡しとなる“ある1本”があるのですが、監督たちと話して共通する視点を作ったんです。それは1話に登場する塾の講師を演じているときにふと思いついたもので、映像的に分かりやすく顕在化している訳ではないんですが、不協和音として入れました。かなりの大仕事でしたね。この難解な話を、直接的に残忍なシーンもなく進んでいく中、何が男の真意かも分からない。各話に登場するゲストの方々ですら、その回の台本しか渡されていないので何のことか分からず、「誰が犯人なんですか?」と聞いてくる訳です。そんなこともあって1本橋渡しをする作業を、ドラマの中でトリガーを引く瞬間として作りました。

――「橋渡し」とは具体的にどのようなものですか?
香川 例えば、同じ動作をすることで、それが男のスイッチが入る瞬間だと。でも、それだと分かりやすいから、いくつか僕から提案して、その中から「これでいきましょう」というのを決めました。「編集でカットしてもいいから」と伝えていましたが、完成した作品を観たら、上手い具合に残されていました。一回観ただけでは気づかないでしょうし、違和感として、ポイントとして作っています。以前にも同じような試みをやったことはありますが、今回のドラマだからこそできる力点を、監督と僕と3人で秘密裏に作り、その力点が生じる役者さんには、「こういう力点を作りますから、こういう反応をしていただいてもいいですし、しなくてもいいです。自分の好きなことでいいですし、それを楽しんでください。あとで編集できますから」という形で僕が事前に説明しました。
――香川さんから提示するんですね。
香川 僕から説明する方が一番早いと思ったんです。役者同志なので、役者の言葉で説明したほうがキャッチしやすいですからね。
――ゲストの方々の印象はいかがでしたか。
香川 皆さんおうちから持ってきてくださったものが、どれも上質で、なぜか5月組の空気感を分かってくれていたんですよね。年齢に関係なく、十代の役者さんも本当に素晴らしい“間”でしたし、現場で生まれるものを楽しんでくださっているなと感じました。
――『宮松と山下』の試写会で、5月の方々が香川さんを「顔全体が可動域のようでした」と評していましたが、今回はいかがでしたか。
香川 前回は僕の顔を稼働させないように、ずっと3人に縛られていて、「顔を動かさずに普通にいてください」と言われていたんです。それに対して僕は、久しぶりに何が普通かを旅して面白かったんですよね。それを糧にして、今回は同じ轍を踏まないようにと極力、顔の可動域を使わないようにして、いろんな役をやったつもりではありますが、ある場面で稼働させたら監督たちは大喜びしていました。